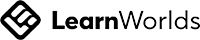倒産寸前?企業の“最後の価値”を測る清算バリュエーションとは
Jun 17
/
ザ・モデラズ
清算価値法(Liquidation Valuation)とは、企業が保有するすべての資産を売却し、負債を返済した場合に創出される純現金(Net Cash)を推定する手法です。この方法は、一般的に経営不振(Distressed)または非営業状態(Non-Operating)にある企業に適用され、資産が強制売却(Forced Sale)される際に実際に回収可能な金額を反映するため、保守的かつ割引された価値が与えられます。
したがってこの方法は、破産や債務不履行(Insolvency)の状況、担保評価(Collateral Assessment)、業績不振またはノンコア資産(Non-core Assets)の売却価値(Exit Value)の評価などに幅広く活用されます。
清算価値法を実行する際、アナリストはまず、有形・無形固定資産を含む企業の全資産を洗い出し、強制売却(Forced Sale)または整然売却(Orderly Sale)の条件下での実現可能価値(Realizable Value)を推定します。このとき、多くの場合、帳簿価額に対して大幅な割引率(Discount)が適用されます。
次に、担保付き(Secured)および無担保(Unsecured)の負債(Debt)、買掛金(Accounts Payable)、その他のすべての未払債務(Outstanding Obligations)を全額控除して、株主に帰属する純清算価値(Net Liquidation Value)を算出します。
しかし、清算価値法は「企業がまもなく営業を停止する」という仮定に基づくため、健全に営業を続けている企業には頻繁に用いられるものではありません。この方法は、将来の収益可能性だけでなく、一部の無形資産価値や企業の戦略的価値を無視する傾向があるため、企業価値を過小評価(Undervalue)しやすく、主に投資家や債権者が最悪のシナリオにおける価値の下限(Valuation Floor)として利用します。
清算価値法(Liquidation Valuation)の実施手順
具体的には、以下のような手順で進めるのが一般的です。
1. 保有資産の特定と分類
清算価値評価の最初のステップは、企業が保有するすべての資産を特定し、適切に分類することです。資産は通常、流動資産(現金、売掛金、在庫など)と非流動資産(土地、建物、設備、ブランド、特許など)に分けられ、それぞれの資産項目の数量、帳簿価値、使用状況などを詳細に検討し、評価の基礎資料とします。
2. 資産別清算価値の推定(Net Realizable Value)
各資産が清算過程で実際にどの程度現金化できるかを推定します。通常の売却ではなく、強制処分(fire sale)の状況を前提とするため、一般的にかなりの割引率が適用されます。
例:在庫資産は30〜50%、機械設備は20〜40%といった具合に、現実的な市場価格を反映させる必要があります。
無形固定資産の場合、ブランド認知度やライセンスの有効期間などを考慮し、清算時に回収可能かどうかを評価します。
3. 総資産処分収益の算出
ステップ2で算出した各資産の清算価値をすべて合計して、総処分収益を算出します。このとき、資産を売却する際に発生する可能性のある各種取引コスト—たとえばブローカー手数料、弁護士費用、税金、輸送費など—を反映して、実際に回収可能な純収益を導出します。これが実質的な清算資産の規模を表します。
4. 優先順位に基づく債務の弁済
清算で得た現金は、法律および契約上の優先順位に従って、債権者および投資家に分配されます。
一般的には、担保付き債権者(例:担保付きローン、未納税金)から優先的に返済され、その後、劣後債権者、優先株主、最後に普通株主の順で分配されます。企業の負債が多い場合や資産価値が低い場合、債権者でさえ全額返済されないこともあります。
5. 残余価値の計算と株主価値の算出
すべての債務を返済した後に残った金額がある場合、それは企業の株主に帰属します。しかし、多くの清算事例では残存価値がほとんどない、もしくはマイナスになるケースもあります。このように残存価値が存在しない場合、普通株の価値は0と評価され、その企業の株式は無価値と見なされます。この結果は、破産手続きや投資損失評価の重要な基準となります。